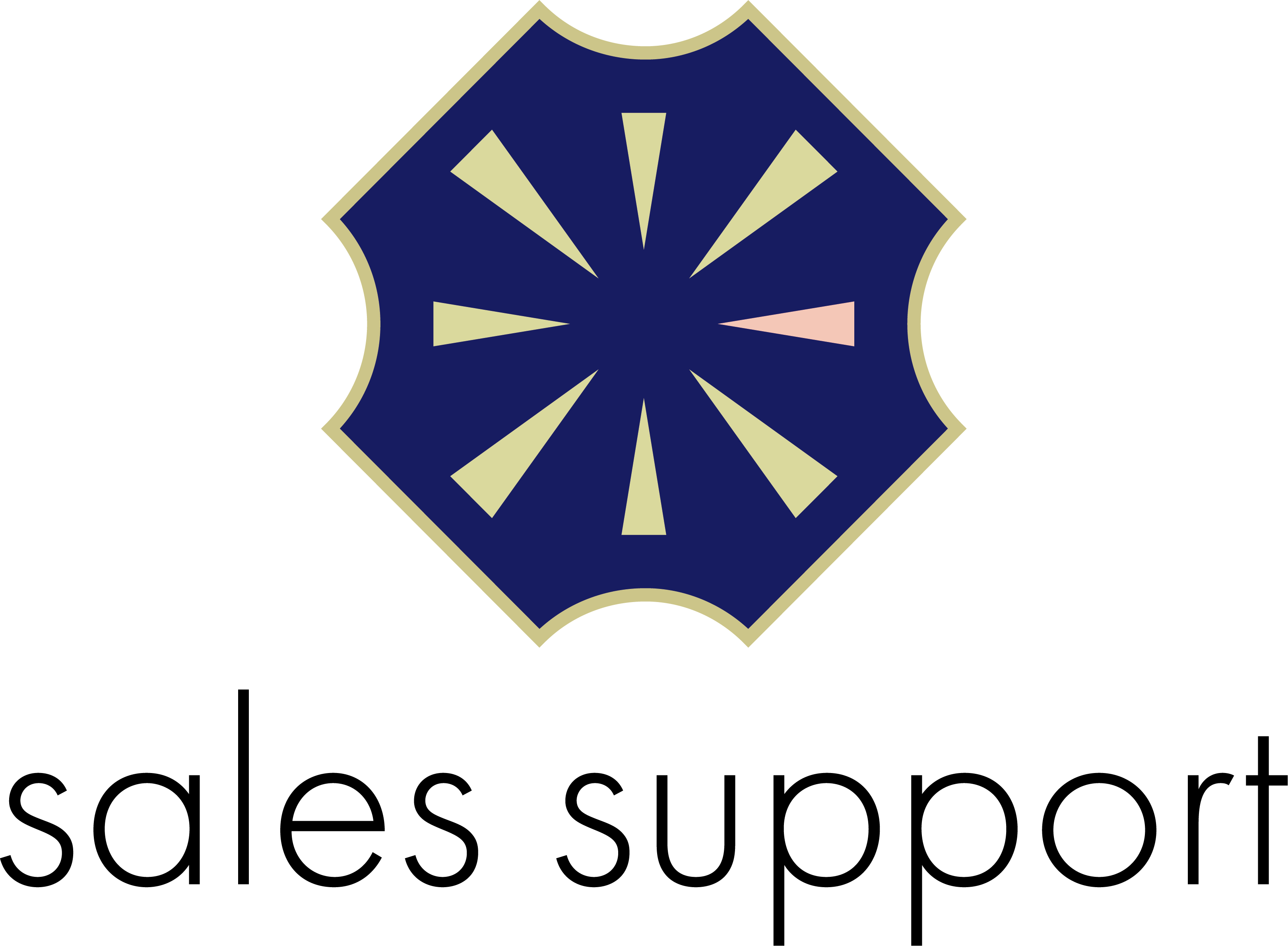こんにちは。
最近、こんなことを考えることが増えました。
「診断士って、公的支援ばかり。
補助金以外で、民間契約で経営支援している人って、どのくらいいるんだろう?」
今日は、そんな視点から【診断士の契約形態の実態】と、【民間契約で経営伴走している人たちの事例】をご紹介したいと思います。
Table of Contents
診断士の契約形態の実態
中小企業診断士の支援スタイルは、主に3つに分けられます。
① 公的支援中心型(全体の6〜7割)
-
商工会・商工会議所の派遣や、自治体の専門家登録制度による活動が中心。
-
「無料相談」や「補助金申請支援」が多く、定期契約ではないことも。
② 補助金メインの民間契約型(2〜3割)
-
民間企業からの依頼でも、目的は補助金や認定支援機関での書類作成。
-
成果物納品型で、顧問や伴走契約には至らないケースが多い。
③ 経営の伴走支援を行う純民間契約型(1〜2割未満)
-
補助金に依存せず、経営戦略・集客・ブランディングなど継続支援がメイン。
-
クライアントとの“関係性”に基づいたコンサルスタイルが多い。
なぜ、純民間契約は少ないのか?
純民間契約の診断士が少ない背景には、いくつかの理由があります。
-
診断士=補助金、というイメージが強い(企業側もそう思っている)
-
伴走支援の対価として、月額料金をいただく文化が根付いていない
-
営業・発信が苦手な診断士が多く、集客につながらない
-
「何をしてくれるか」が見えづらく、契約まで結びつきにくい
一言でいえば、価値の“伝え方”と“売り方”の課題が大きいのです。
民間契約で活躍する診断士の3タイプ
それでも、民間で経営支援をしている診断士は確かに存在します。
彼らには、ある共通点があります。それが下記の3タイプです。
① 業種特化型(美容院・整体・飲食店など)
-
特定業界に特化し、業界構造・慣習・顧客ニーズを深く理解。
-
業界内での認知度を高め、リピート顧問契約がしやすい。
-
例:美容院専門で集客・価格設計・人材育成を支援
② スキル特化型(元コンサル・元マーケター)
-
自身の実務スキル(財務・WEB・マーケティング)を武器に活動。
-
明確な「成果のあるスキル」を求める企業とマッチしやすい。
-
例:元広告代理店出身 → 小規模B向け販促戦略の月額支援
③ 地方密着・関係性重視型
-
地域の中小企業と「人と人」のつながりで支援を構築。
-
経営会議参加・数値管理・販促まで幅広くサポート。
-
クチコミ・紹介で少数精鋭の顧問先を持つ
共通する成功ポイントは「価値の言語化」と「選ばれる理由の明確化」
民間契約を実現している診断士には、次のような共通点があります。
-
明確なターゲット(WHO)がある →「誰の役に立ちたいか」がはっきりしている
-
成果物より、変化の提供に価値を置いている →レポートより「一緒に前に進めた」体験を重視
-
サービス内容が具体的で、価格も明示している →「頼みやすい」「比較しやすい」が信頼につながる
-
発信・営業に自分の“言葉”で取り組んでいる →SNS・ブログ・セミナーなどで価値を見える化
まとめ:診断士の「本当の可能性」は、まだまだ広がっている
中小企業診断士の資格は、単なる「補助金サポーター」にとどまりません。
むしろ、小さな事業者に寄り添い、想いを整理し、経営を支える伴走者としての可能性は、これからもっと必要とされていきます。
あなた自身の強みや経験を活かし、誰かの“本気”に火をつける支援をしていきたい──
そんな診断士がもっと増えたら、きっと日本の中小企業は元気になります。